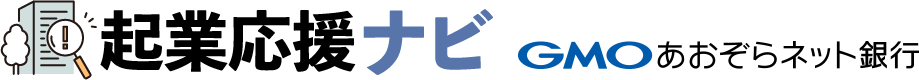多くの中小企業にとって、売上1億円という数字は一つのマイルストーンです。
しかし、そこを超えた企業が次に直面するのは、「売上が伸びても利益が増えない」という問題です。
この問題は、“利益が残らない経営構造”に起因しています。
人件費、広告費、外注費、原価、家賃など、売上と共に膨らむコスト。これらを正しく管理しなければ、利益率はむしろ下がってしまうのです。
多くの経営者は、順調な売上に安心し、コストの管理が疎かになりがちですが、その先には利益を生み出す力があるのです。
本記事では、企業が利益を最大化するための実践的なコスト管理の方法を解説します。
目次
1.コストを「見える化」して継続的に管理する

経営において、最も恐ろしいのは「何にどれだけコストを使っているかが分からない」状態です。
社長1人で事業運営をしている場合は、容易にすべてのコストを把握できます。しかし、事業が軌道に乗り、売上が1億円を超えて従業員も増えてくると、次第にコストの全体像が見えづらくなるのです。
売上が順調でもコスト管理が適切にされていなければ利益は出ません。
以下の方法を参考に、利益を最大化するためのコスト管理を始めましょう。
1-1.部門ごとに支出項目をリスト化する
まずは、部門ごとに支出項目を細かくリスト化し、どこにどれだけのコストがかかっているのかを可視化します。例えば、営業部門なら広告費、交通費、事務用品などを分けて記載し、管理部門なら人件費やオフィス関連の支出を整理します。
1-2.「売上に貢献しないコスト」を特定する
次に、各支出項目がどれほど売上に貢献しているかを評価します。
例えば、広告費やマーケティング費用は、施策ごとに売上への貢献度合いを評価します。単なる感覚や経験則ではなく、定量的なデータを基に分析することが大切です。事務用品や消耗品などは直接的な売上向上には寄与しませんが、必要以上に費用を使っていないかを確認します。
1-3.変動費と固定費に分けてコストバランスを最適化
続いて、それぞれのコストに優先順位を付けます。優先順位付けは、コストを変動費と固定費に分けて考えるとスムーズに進められます。
| 変動費 | 売上に応じて増減する費用。売上が増えればその分必要となるコストが増える。 (例)原材料費、人件費、配送費用など |
|---|---|
| 固定費 | 売上に関係なく毎月一定額が発生する費用。 (例)家賃、設備費、ソフトウェアやクラウドサービスの月額料金など |
固定費の削減は利益最大化に直結するため、削減可能な項目があれば、優先的に手を付けるべきです。例えば、オフィススペースの縮小や、サブスクリプションサービスの解約などが挙げられます。
一方で、変動費は売上や市場環境により変動するため、適切なコントロールが必要になります。状況に応じて、仕入れ先との価格交渉や過剰在庫の削減などに取り組みましょう。
また、業務プロセスの効率化を図ることで人件費を抑える方法も有効です。自動化ツールや業務改善を取り入れることで、従業員がより付加価値の高い業務に集中でき、結果としてコストバランスの最適化につながります。
1-4.定期的なレビューと分析を行う
支出項目のリスと化やコスト最適化施策の結果は定期的にレビューと分析を行い、継続してPDCAを回していきます。月次や四半期ごとにコスト管理会議を定例開催し、コスト管理について議論を深める場を設けることも重要です。
2.「キャッシュフロー経営」の意識を持つ

企業の成長に伴い、大手の取引先からの受注が増えると、一般的には売掛金が入金されるまでの期間が伸びていきます。その間も在庫管理や設備投資にお金がかかるため、資金負担が増していくのです。
こうした状態を避けるには、手元に現金が残る仕組み作りと、現金の残高の日常的なチェックを行い、「キャッシュフロー経営」の意識を持つことが重要です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1.手元に現金が残る仕組み作り
売上を上げるだけでなく、手元に現金を残すことにも注力して取り組みましょう。具体的には、以下の方法が挙げられます。
・入金サイトを短縮する(可能な限り一括前払いの契約を結ぶ、売掛金の早期回収に努める)
・出金サイトを延長する(仕入れ先に期日の延長や分割払いの交渉をする)
・在庫の適正管理を行う(過剰在庫にならないように日々在庫量をチェックする)
2-2.キャッシュフローの日常的なチェック
経営状況の確認は、損益計算書や貸借対照表だけでは不十分です。キャッシュフロー計算書や資金繰り表も作成し、日常的にチェックする習慣をつけましょう。
すべてを経理に任せず、社長自身も未来のお金の流れを予測し、あと何カ月資金がもつのかを予測しておくことが重要です。そうすることで、深刻な事態に直面する前に銀行からの借入れを行うなど、適切な経営判断ができるようになります。
3.従業員のパフォーマンスを高める

売上が1億円を超えてくると、業務の拡大に伴って従業員を増やすことが一般的です。
ここで見落とされがちなのが、「従業員と社長ではコスト意識や仕事のパフォーマンスに差がある」という事実です。
この前提のもと、社員のパフォーマンスを高めて生産性を向上させる施策を講じる必要があります。
3-1.従業員と社長のパフォーマンスに差がある理由
社長自身が営業していたときには、結果を出すために時間も労力も惜しまず動き、費用対効果を常に意識していたはずです。
しかし、同じ業務を従業員に任せた場合、同じようには契約が取れなかったり、目先の売上のために追加サービスを付帯して利益率の低い契約を取ってしまったりすることがあります。営業以外の事務的な作業においても、従業員は「業務をこなす」ことに重点を置きがちで、「会社の利益に直結しているかどうか」までは意識が回らないケースが多いです。
では、この差を埋めるためにはどうしたら良いのでしょうか。
3-2.仕事の目標と意義を明確に伝える
こうした“見えない生産性の低下”を防ぐには、従業員に「なぜこの仕事をやるのか」「どんな成果が期待されているのか」を伝え、業務の意義と目標の両方をセットで共有することが重要です。
目標を設定する際は、「売上を増やす」などといった大まかな表現ではなく、「粗利100万円」「新規受注10件」「食品廃棄率5%削減」のように明確な数字を必ず用いるようにします。
設定した目標に対しては、必ず定期的なフィードバックを行い、役割の再分担や外注の検討を行いましょう。
3-3.業務フローの仕組み化
社長自身が業務をこなしていた頃のようなパフォーマンスを従業員にも発揮してもらうためには、業務フローを細分化し、誰がやっても一定の品質を保てる仕組みを作ることが重要です。
しかし、高度な判断力や創造力を必要とする業務までをマニュアル化するのには限界があります。そこで重要なのは、仕組み化できる業務と、仕組み化できない業務に分別することです。
例えば、定型的な事務作業は、マニュアル化することで誰でも同じ品質を保つことができます。これにより、ミスや無駄を減らし従業員が効率よく仕事を進められるようになります。
一方、高度な専門知識や経験が必要な仕事は、あえてフロー化を避け、そのスキルを持つ社員に任せたり、適切なトレーニングを通じて従業員のスキルを向上させたりすると良いでしょう。
3-4.コスト意識を浸透させる
従業員は、会社の予算を自分ごととして捉えることができずにコスト意識が薄くなりがちです。コスト意識を浸透させるためには、以下の3点を行うと良いでしょう。
・現場のチーム単位や従業員単位でコスト削減目標を設定し、定期的に実績を評価する
・コスト削減のアイデアを従業員から募り、改善提案を奨励する
・コスト削減は企業成長に直結するため、一人ひとりが責任を持って取り組むべき重要な施策であるということを根気強く伝える
まとめ
売上1億円を超えた企業が次に取り組むべき課題は、「利益の最大化を目指したコスト管理」です。
売上が伸びていても慢心せず、現在かかっているコスト、キャッシュフローの状況、自社の従業員としっかり向き合って利益の最大化を追求していきましょう。
「売上」ではなく「コスト」を制すことが、安定的な企業の成長を実現する鍵となります。
※ 本コラムは2025年4月1日現在の情報に基づいて執筆したものです。
※ 当社広告部分を除く本コラムの内容は執筆者個人の見解です。