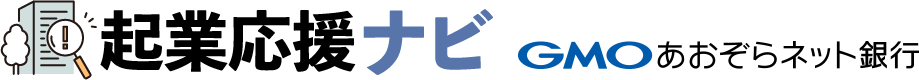多くの中小企業の経理担当者が抱えるお悩みに、「月末・月初の振込業務で残業が続く」「二重払いや支払い漏れのミスが心配で何度もチェックしている」「請求書処理に膨大な時間がかかっている」などがあります。
人手不足が深刻化する中、経理部門の業務負荷はますます増大しています。
しかし、これらの課題は決済業務の自動化によって根本的に解決できることをご存じでしょうか。
実際に決済業務を自動化した企業では、経理部門の業務時間を最大70%削減し、ミスが大幅に減少し、働き方改革も同時に実現しているケースは珍しくありません。
本記事では、自動化ツールの導入方法と、その効果について詳しく解説します。
目次
1.決済業務の現状と中小企業が抱える課題とは?
中小企業の経理担当者の中には、以下のような手作業を中心とした決済業務をされている方もいるのではないでしょうか。こういった非効率な業務は、担当者の負担増加や、ケアレスミスの発生の原因にもなりえます。
●手作業で行われる決済業務の例| 請求書処理 | 取引先からの請求書を手作業で会計システムに入力し、内容確認や承認フローを経て支払い処理を実行。一件あたり平均15-20分の時間を要し、月間数百件の処理では膨大な工数が発生します |
|---|---|
| 振込業務 | 銀行の窓口やネットバンキングで一件ずつ振込処理を実行。振込先情報の入力ミスや金額間違いのリスクが常に存在し、確認作業に多くの時間が割かれます |
| 入出金照合 | 通帳記載内容と会計データを目視で照合し、不一致があれば原因調査を実施。この作業だけで月末に丸一日を要する企業も少なくありません |
| 時間的負荷 | 月末月初の集中的な業務で、経理担当者の残業時間が月20-30時間増加する |
|---|---|
| 精神的負荷 | ミスが許されない緊張感の中での長時間作業で、担当者が疲弊する |
| ミスリスク | 人的作業による入力ミス、重複処理、支払い漏れなどが定期的に発生する |
| 機会損失 | ルーティン業務に追われ、本来優先度が高い財務分析や戦略的業務に時間を割けない |
2.決済業務自動化がもたらす3つの劇的な好影響
ここからは、決済業務を自動化する方法と、それによる業務時間の削減効果を紹介していきます。
2-1. 請求書データの自動取り込みによる入力作業の改善
こちらのケースは、OCR技術で請求書処理を自動化し、従来20分かかっていた作業を2分に短縮。月間60時間の作業時間削減と、入力ミスの大幅減少を実現しました。
製造業A社の例(従業員50名)
| 従来の方法 | 請求書を受領後、担当者が手作業で金額、支払い期日、取引先情報などを会計システムに入力 |
|---|---|
| 自動化後 | OCR(光学文字認識)技術を活用し、請求書をスキャンするだけで必要な情報を自動抽出・入力 |
| 削減効果 | • 1件あたりの処理時間:20分 → 2分(90%削減) • 月間200件処理の場合:67時間 → 7時間(60時間削減) • 入力ミス発生率:5% → 0.1%(50分の1に減少) |
\請求書処理の自動化におススメのサービス/

GMOあおぞらネット銀行では、請求書のアップロード、支払いの申請・承認、振込実行から電子保管までワンストップで行える法人のお客さま向けのサービスを提供しています。詳細はこちらからご確認ください。
2-2.振込・支払いの自動処理による承認フローの高速化
以下のケースでは、システム上での電子承認と一括振込処理により、承認プロセスが3日から1時間に短縮し、支払い業務の大幅な効率化を実現しました。商社B社の例(従業員30名)
| 従来の方法 | 承認者への書面での確認、印鑑押印、銀行での個別振込処理という多段階のプロセス |
|---|---|
| 自動化後 | システム上での電子承認と一括振込処理により、ワンクリックで複数の支払いを同時実行 |
| 削減効果 | • 承認プロセス:平均3日 → 1時間以内(95%削減) • 振込処理時間:1件5分 → 一括処理で全体10分 • 月間80件の処理の場合:72時間 → 2時間(70時間削減) • 承認者の負荷:書面確認からシステム上のワンクリック承認へ |
2-3.入出金の自動照合によるチェック作業の完全自動化
最後は、銀行API連携で入出金データを自動照合し、月次の照合作業が8時間から30分に短縮し、照合精度も99.9%に向上したケースです。小売業C社(従業員25名)の例
| 従来の方法 | 銀行通帳と会計帳簿を目視で一件ずつ照合し、不一致項目を手作業で調査 |
|---|---|
| 自動化後 | 銀行API連携により、入出金データを自動取得・照合し、例外項目のみを担当者に通知 |
| 削減効果 | • 月次照合作業:8時間 → 30分(94%削減) • 照合精度:95% → 99.9%(人的ミスの排除) • 不一致項目の発見速度:月次 → リアルタイム |
3.具体的な業務削減シミュレーション
従業員数30名程度の中小企業を想定し、決済業務自動化による削減効果を試算してみましょう。
| 導入【前】の業務時間 | 導入【後】の業務時間 |
|---|---|
| • 請求書処理:150件×20分 = 50時間 • 振込業務:80件×10分 = 13時間 • 入出金照合:月末集中作業 = 8時間 • 支払い確認・督促:月5回×2時間 = 10時間 ➡合計:81時間/月 |
• 請求書処理:150件×2分 = 5時間 • 振込業務:一括処理 = 2時間 • 入出金照合:自動照合確認 = 1時間 • 支払い確認・督促:自動通知確認 = 2時間 ➡合計:10時間/月 |
年間削減時間:852時間
人件費削減効果:年間約213万円 ※時給2,500円で計算
この削減された時間を財務分析、予算管理、経営支援などの戦略的業務に活用できれば、課題であった機会損失を回避できます。
4.決済業務自動化のステップガイド
決済業務を自動化するにあたって必要な4つのステップをご紹介します。
ステップ1:現状業務の詳細な分析と課題の明確化
まずは、現在の決済業務を定量化し、課題を洗い出し分析します。
| 業務の定量化 | • 月間処理件数の集計 • 業務別の所要時間測定 • 担当者別の業務負荷分析 • 繁忙期の業務集中度合いの把握 |
|---|---|
| 課題の洗い出し | • 頻発するミスの種類と発生原因 • 業務ボトルネックの特定 • 担当者の負荷状況と改善要望 • 取引先からの苦情や要望の整理 |
ステップ2:自動化ツールの選定と要件定義
自社の要件にあった決済自動化ツールを選定するためには、「機能要件の整理」「導入時の検討項目」の確認が必要です。実施の際は、以下のポイントを参考にしてください。
<機能要件を整理する際のポイント>
・既存会計システムと連携しているか
・取引銀行との接続には対応しているか
・承認フローのカスタマイズ機能は十分か
・セキュリティレベルと監査証跡機能はあるか
<導入時に検討する際のポイント>
・導入形態をクラウド型/オンプレミス型どちらのタイプにするか
・月額料金と初期費用の価格を比較した際に適正か
・充実したサポート体制と導入支援があるか
・中長期的な機能拡張の可能性があるか
ステップ3:段階的な導入と運用定着
一度にすべての業務を自動化するのではなく、段階的に導入する方が導入のハードルを下げられます。
|
フェーズ1 (1-2カ月) |
• 請求書の自動読み取り機能から開始 • 少数の取引先でのテスト運用 • 担当者の操作習熟と課題の洗い出し |
|---|---|
| フェーズ2 (3-4カ月) |
• 振込業務の自動化を追加 • 承認フローの電子化 • 全取引先への展開 |
| フェーズ3 (5-6カ月) |
• 入出金照合の完全自動化 • レポート機能の活用開始 • 運用ルールの確立と標準化 |
ステップ4:効果測定と継続改善
決済業務を自動化したら、効果を定量的、定性的に測定し継続的な改善を図ります。
| 定量効果の測定 | • 業務時間の削減実績 • ミス発生率の低下状況 • 担当者の残業時間の変化 • 支払い期日遵守率の向上 |
|---|---|
| 定性効果の評価 | • 担当者の業務満足度 • 取引先からの評価変化 • 経理部門の戦略業務への関与度 • 組織全体のデジタル化進展度 |
5.導入時の注意点とリスク管理
ここでは、決済業務の自動化にあたって、大きく3つの考慮すべき注意点とリスク管理についてご説明します。
5-1.セキュリティ対策の徹底
金融情報を扱うため高度なセキュリティ対策が必要となります。
具体的には、以下の4つが挙げられます。
・職務に応じた最小権限の原則によるアクセス権限の厳格な管理
・すべての処理履歴を保存する操作ログの完全記録と監査機能
・保存データと通信データの両方を暗号化する対策
・外部専門機関による定期的な脆弱性診断などのセキュリティ監査
これらの対策により、金融データの安全性を確保しながら効率的な決済業務の自動化を実現できます。
5-2.内部統制の維持・強化
決済業務の自動化においても、内部統制の維持・強化が重要です。
承認者と実行者を分離する職務分離の原則を維持し、システム障害時の代替手順を明文化した例外処理を整備する必要があります。
また、自動処理の精度を確認するために、定期的な手作業でのサンプルチェックを実施し、会計監査に対応できる監査証跡の整備を行うことで、自動化と内部統制の両立を図ることができます。
これらを対策することで、効率性と信頼性を両立した決済業務体制を構築できます。
5-3.担当者のスキルアップ支援
担当者のスキルアップ支援も重要です。
定期的な操作研修の実施により、システム操作の習熟を図るとともに、自動化により削減された時間を活用して、財務分析スキルの向上に取り組む必要があります。
また、イレギュラーケースへの対応力を高める例外対応能力の強化や、IT技術の基礎知識習得によるデジタルリテラシーの向上も重要です。
これによって、自動化されたシステムを効果的に活用できる人材を育成し、経理業務全体の質的向上を実現できます。
6.決済業務の自動化を成功させた3社の事例
最後に、GMOあおぞらネット銀行の法人口座を活用して、決済業務の自動化を成功させたお客さまの事例を紹介します。
6-1.株式会社ネクスト・ブレインさま

入学検定料や学費などの請求管理をオンライン上で行える「SchoolDB」という学校運営に最適化された業務アプリケーションシステムへ振込入金口座(バーチャル口座)の参照系APIを活用しています。
GMOあおぞらネット銀行の振込入金口座(バーチャル口座)は、入金専用の口座番号をユーザーごとや取引ごとに割り当てることができます。そのため、銀行振込による入金管理がスムーズに行えるわけです。
具体的には、振込入金口座(バーチャル口座)の発行、削除などをAPIで自動化し、さらに入金された明細情報をAPIで取得することで、入金消込を自動化しました。
これにより、学校法人さまは、検定料や授業料といった膨大な入金確認の特定が容易になり、これまで手動で行っていた入金情報が自動で反映されるため、手作業で行っていた入金消込や入金確認の手間を省くことができるようになりました。"
6-2.株式会社マネーコミュニケーションズさま
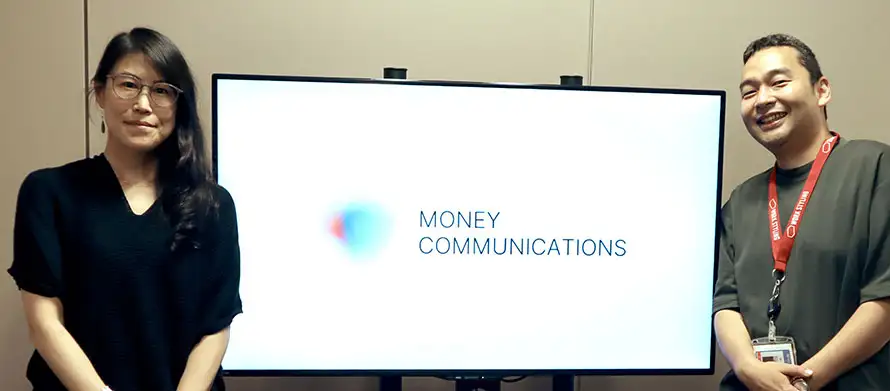
給与前払いサービス「プリポケ」のサービス利用者(アプリ会員)が給与前払い申請を行うと、その申請に基づき更新系APIを用いることで、申請とほぼ同時に送金が実行されます。
以前は手作業で送金処理をし、サービス利用者へ給与の前払いを行っていました。今回、銀行APIを活用することで自動的に送金することができるようになり、即時性が高まるだけでなく送金処理の事務作業の手間がぐっと削減できました。
6-3.共栄商工株式会社さま

GMOあおぞらネット銀行の場合、振込手数料が同行間であれば無料、他行であっても143円と安価ですし、何より定額自動振込の機能があるのでいちいち振込手続きの面倒がありません。コストと手間の削減になっているのも満足しているポイントです。
まとめ
中小企業の経理担当者が抱える決済業務の課題を解決するには、決済業務の自動化が不可欠です。一口に、決済業務の自動化といってもさまざまな方法があります。まずは、自社の課題を洗い出し、それに応じた自動化方法や導入ステップを導入時のリスクを加味して進めるのが成功のポイントです。
※本コラムは2025年8月1日現在の情報に基づいて執筆したものです。
※当社広告部分を除く本コラムは執筆者個人の見解です。