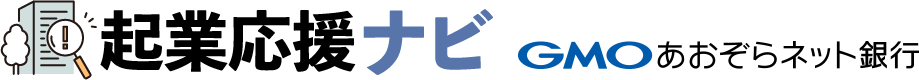会社を設立することは、事業を本格的に始めるための大切な一歩です。法人化によって社会的信用が高まり、融資や投資など資金調達の手段も広がります。
その一方で、登記や資本金の準備、各種届出などの手続きが必要で、注意点も少なくありません。本記事では、会社設立のメリットや流れ、注意すべき点、資金調達方法までを分かりやすく解説します。
1.会社を設立するメリット

会社を設立するメリットは多岐にわたります。ここでは代表的な4つのポイントを取り上げ、解説します。
1-1.社会的信用の向上につながる
法人化すると、取引先や金融機関からの信頼が得やすくなります。
契約や融資の場面でも有利になり、公共事業や大手企業との取引機会も増える可能性があります。ただし、信用を維持するには、適正な帳簿管理や税務対応が不可欠です。
1-2.資金調達の多様化につながる
法人格を持つと、銀行融資やコーポレートカードの利用ができるようになり、将来的には投資家からの出資やIPOなどの選択肢も生まれます。
個人事業主に比べて与信(運転資金の枠)が得やすく、調達できる資金規模も大きくなるのが利点です。一方で、資本政策や投資家対応の負担も伴います。
1-3.税制関連の恩恵が多い
法人化すると、役員報酬や退職金の損金算入が可能になり、経費計上の幅が広がります。中小法人向けの軽減税率や欠損金の繰越控除など、税制上の優遇措置も多いのが特長です。
ただし、社会保険料の負担増など別のコストも発生するため、税理士に相談しながら計画することが大切です。
1-4.優秀な人材の確保がしやすい
法人を設立すると、雇用が安定したり福利厚生の整備がしやすくなったりと、人材採用に有利にはたらきます。
賞与や退職金制度に加え、ストックオプションなど多様な報酬制度を導入できる点も魅力です。一方で、人材定着には給与水準の確保や評価制度の整備が欠かせません。
2.会社を設立するまでの流れ

会社設立は、法人情報決定→実印作成→定款作成→資本金払込→登記申請の順に進めます。それぞれについて詳しく解説します。
2-1.法人の基本情報を決める
会社設立の第一歩は、法人の基本情報を固めることです。主な項目は下記のとおりです。
●法人形態(株式会社・合同会社など):組織の仕組みや対外的な印象、手続きの違いに影響します。
●商号(会社名)と本店所在地:登記住所は後で変更可能ですが、事業上の利便性を考慮しましょう。
●事業目的:将来の事業展開を見越して広めに書く一方、許認可が必要な業種は明記しておきましょう。
●事業年度(決算期):決算タイミングは税務や資金繰りに関わります。
●資本金・発行株式数:資本金は1円からでも可能ですが、信用や運転資金を考えて設定します。
●役員構成・代表者:代表者や取締役の人数、任期などを決めます。
●株式譲渡制限の有無や公告方法などの定款に関する事項。
ポイントは、複数案を用意し、必要に応じて行政窓口や専門家に相談しておくことです。これらを決めておけば、次の定款作成や登記手続きがスムーズになります。
2-2.会社実印を作成する
2021年2月15日から、登記申請をオンラインで行う場合の印鑑提出が任意になりました。
しかし、未だ多くの場面で実印を求められる可能性があるため「会社の実印(代表印)」を作成しておくと安心です。法務局に登録すれば印鑑証明書が発行され、銀行口座開設や契約時に利用できます。
2-3.定款を作成する
定款は会社の基本ルールを定める重要書類です。株式会社では公証人の認証が必要ですが、合同会社は不要です。
紙定款には印紙税がかかりますが、電子定款なら非課税で作成できます。将来の事業拡大や株式の譲渡制限なども考慮し、司法書士や行政書士に相談するのも有効です。
2-4.資本金を払う
定款作成・認証が終わったら、設立登記の前に資本金の払い込みを行います。一般的には代表者の個人口座に入金し、通帳写しや払込証明書を準備します。
資本金は1円から設定可能ですが、信用や運転資金の面を考えると十分な額を用意するのが望ましいでしょう。登記完了後は法人口座へ振り替えます。
2-5.登記申請書類を用意し登記申請する
登記は会社設立の最終段階です。必要書類を揃え、登録免許税を納めて管轄の法務局に申請(窓口または登記・供託オンライン申請システム)します。申請後、通常1〜2週間程度で登記が完了し、法人番号が付与されます。
主な提出書類(株式会社の場合)
●登記申請書
●公証人の認証を受けた定款(原本)
●資本金の払込を証する書面(払込証明書や通帳の写し)
●取締役の就任承諾書
●代表者の印鑑届出書および印鑑証明書
●必要に応じて委任状や株主リストなど
合同会社は定款の公証が不要で、登録免許税は株式会社が最低15万円、合同会社は6万円が目安です。書類に不備があると差戻しになるため、事前に法務局の様式を確認するか司法書士に依頼すると安心です。
3. 会社設立後にやるべきこと
会社の登記が完了したら、いよいよ事業スタートの準備です。
とはいえ、登記が終わったあとにも「やるべきこと」は意外と多くあります。ここでは、設立後に早めに対応しておきたい代表的な手続きを整理しておきましょう。
3-1. 税務署・年金事務所などへの届出
会社を設立したら、まずは各行政機関への届出が必要です。特に以下のような書類は、提出期限も決まっているため早めに準備しましょう。
●税務署への提出書類
(法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など)
●年金事務所への提出書類
(健康保険・厚生年金保険の新規適用届、被保険者資格取得届など)
●労働基準監督署・ハローワークへの提出書類
(労働保険の保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届など)
これらを放置してしまうと、後から追加入力や罰則の対象になる可能性もあるため、登記完了後すぐに着手しておきましょう。
3-2. 法人銀行口座を開設する
会社を設立したら、法人名義の銀行口座を開設することも欠かせません。
法人のお金の流れを明確にすることで、経理処理や税務対応がスムーズになるほか、取引先や補助金申請などで法人名義口座の提示を求められるケースも一般的です。
ただし、銀行によっては「設立間もない会社」や「バーチャルオフィス登記の法人」は、口座開設の審査が通りにくいこともあります。
そのため、オンライン手続きに対応していて、創業期の企業にも柔軟な銀行を選ぶことが大切です。
\GMOあおぞらネット銀行なら最短即日で口座開設可能/

GMOあおぞらネット銀行の特長
●Web完結で最短即日口座開設可能(※)
●口座開設費・維持費無料
●バーチャルオフィス・固定電話不要
●登記上の設立月から12カ月間、他行宛て振込手数料が毎月20回無料
●国税・社会保険料の口座振替可能
利便性はもちろん、スモール&スタートアップ企業を支えるパートナー銀行として、口座開設後も経営を支援する各種サービスを提供しています。
<ご注意事項>
・審査の状況によりお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・当社休業日にお申し込みいただいた場合は、当日の口座開設はできませんのであらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
・ビジネスデビットカードは当日ご利用いただけません。後日転送不要の簡易書留にてご登録法人住所宛てにお送りいたします。
・当社から送付する郵便物をお受け取りいただけない場合、口座の利用制限やカード・口座解約となる場合がございます。
3-3. 会計ソフトや法人カードを導入する
日々の経理処理を効率化するために、会計ソフトや法人カードの導入もおすすめです。銀行口座と連携すれば、自動で入出金データを取り込み、経費の可視化や帳簿作成を大幅に省力化できます。
法人カードを活用すれば、経費支払いの履歴も明確になり、資金管理の精度も高まります。特に創業期は、個人資産と会社資金の区別をきちんとつけることが、信頼性のある経営につながります。
会社を設立したあとは、「届出」「口座」「会計」の3ステップを早めに整えることがポイントです。これらをスムーズに進めることで、資金管理の基盤が整い、安心して事業をスタートできます。
4. 会社を設立するうえでの注意点

設立手続きや開業準備が整ったら、次に意識したいのは「会社を運営していくうえでの注意点」です。
設立後は社会保険加入や役員報酬の運用ルール、相続対策など法的・税務的な注意が必要です。ここでは特に注意しておきたい3つのポイントを解説します。
4-1.健康保険や厚生年金の加入義務が発生する
法人を設立すると社会保険の適用事業所となり、代表者や従業員は健康保険や厚生年金への加入が原則必要です。保険料は会社と被保険者で折半となり、人件費が増える一方で、傷病手当金や出産手当金などの保障も受けられます。
制度が複雑なため、社労士に相談して準備すると安心です。
4-2.役員報酬の決め方にはルールがある
役員報酬は、法人税法上「定期同額給与」で支給することが基本です。期中の変更は認められにくく、賞与を損金算入するには事前に届出が必要です。
報酬額は会社の損金となりますが、同時に役員本人の所得税や社会保険料が増えるため、資金繰りや税負担を踏まえた設計が欠かせません。
4-3.相続に関する事項にも知識を持っておく必要がある
法人化により事業は会社に帰属しますが、株式は相続財産となるため承継時に経営権が移動する可能性があります。定款で譲渡制限を設けたり、後継者を明確にしたりするなどの対策が重要です。
また、相続税評価や納税資金の準備も必要で、事業承継税制や生命保険の活用も選択肢となります。
5.会社を設立するときの資金調達方法

会社設立には初期費用と運転資金が必要です。ここでは主な方法を紹介します。
5-1.融資
銀行融資は、創業時に利用されることの多い資金調達方法です。民間銀行は、実績や担保を重視するため創業初期は審査が厳しめですが、日本政策金融公庫や信用保証協会付き融資は、無担保・無保証枠があり、利用しやすいのが特長です。
事業計画書などの必要書類を整え、複数機関を比較して選びましょう。
5-2.VCによる出資
成長性の高いビジネスでは、VC(ベンチャーキャピタル)による出資も選択肢になります。資金だけでなく、経営支援やネットワークの提供も期待できますが、株式の希薄化や経営への関与などのリスクも伴います。
事業計画やKPI(重要業績評価指標)を明確に示し、相性の良い投資家を選ぶことが成功の鍵です。
5-3.補助金・助成金
返済不要の補助金・助成金は、資金調達の大きな助けとなります。創業期は「小規模事業者持続化補助金(創業枠)」などが代表的で、雇用関連の助成金も活用できます。
ただし、申請要件は厳格で、報告や領収書の提出も必要です。公募情報は、毎年変わるため、商工会議所や支援機関に確認しましょう。
5-4.自己資金
自己資金は、会社設立で最も手軽かつコストのかからない資金調達手段です。資本金として払い込むか、役員貸付けとするかを区分し、記録を残すことが重要です。
一般的には、半年から1年分の運転資金を確保しておくのが望ましいとされますが、税理士に相談して会計処理を適切に行うと安心です。
5-5.知り合いからの借り入れ
親族や知人からの借り入れは、柔軟で低利の条件を得られる場合がありますが、人間関係が悪化するリスクが大きい点に注意が必要です。必ず契約書を作成し、利率や返済条件を明記しましょう。
無利子や明確な返済期限を定めない場合は、贈与扱いになる可能性があるため、税理士に確認してから進めることをおすすめします。
まとめ
会社設立は、信用力向上や資金調達の幅拡大、税制面の優遇など多くのメリットがありますが、定款作成・登記、資本金の準備、社会保険加入や役員報酬のルールなど留意点もあります。
流れを事前に整理してから資金計画を立て、必要なら税理士や司法書士、創業支援窓口に相談して着実に進めましょう。
※ 本コラムは2025年11月11日現在の情報に基づいて執筆したものです。
※ 当社広告部分を除く本コラムの内容は執筆者個人の見解です。